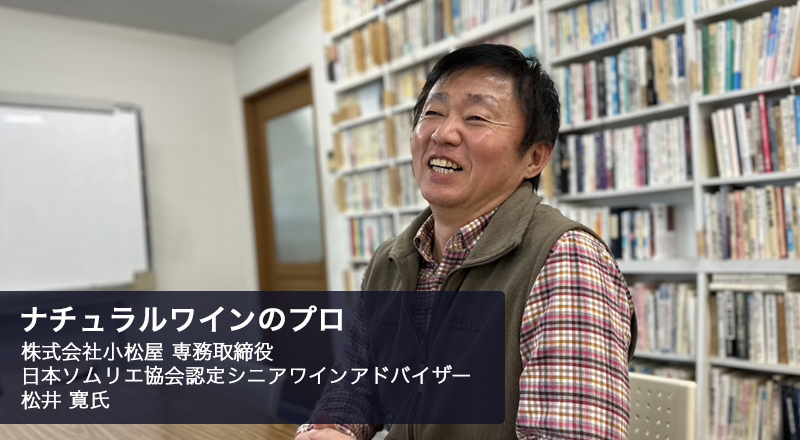
ナチュラルワインに興味はあるものの、実際の選び方や楽しみ方がよく分からない。最近よく耳にするけれど、一般的なワインとの違いも曖昧—。そんな20〜50代の方に向けて、注目を集めるナチュラルワインの魅力から選び方、おすすめの1本までを詳しくご紹介します。
おしゃれで体に優しそうというイメージだけでなく、その本質的な価値や楽しみ方を知ることで、ワインライフがより豊かになるはずです。
今回は、30年以上にわたりナチュラルワインを専門に扱い、数々の生産者との直接取引を行うワインショップ「小松屋」のソムリエ、松井さんにお話を伺いました。
▼ナチュラルワインのまとめ
| 定義 |
|
|---|---|
| 選び方のポイント |
|
| おすすめ商品 |
|
| 保存・楽しみ方 |
|

この記事の目次
初心者向け!専門家に聞く「ナチュラルワインの選び方」

ナチュラルワインに興味を持ったものの、どう選んでよいか迷ってしまう...。そんな方は少なくないのではないでしょうか。実は、ナチュラルワインの選び方は意外と奥が深いのです。
その選び方の難しさの1つが、各国共通の基準が存在しないことです。例えばフランスではビオディナミ農法(※)の認証や有機農法の認証といった基準があります。フランス以外でも、各国でさまざまな基準が存在します。
(※)月の満ち欠けなどの天体の動きに合わせてブドウを育てる農法
また、「価格=ワインの質」という判断も難しいのがやっかい。手間がかかる製法のため、土地の価格や人件費などさまざまな要因が絡み合い、「◯◯円以上のワインを買っておけば失敗しない」とは言い切れないのです。
では、初めてナチュラルワインを選ぶときは、どうすればよいのでしょうか?ここでは、3つの簡単なアプローチをご紹介します。
選び方1:ワインボトルの情報を活用する

1つ目は、ワインボトルに付けられている情報を活用する方法です。
ワインの首に掛かっているタグや認証マーク、コンクールでの受賞歴など、様々な情報が目安になります。認証マークに関しては前述のとおり共通基準がなく、コンクールの受賞に関しても同じくその評価基準は実にさまざまです。ただ、何の指標もないよりは、これらの情報を参考にする方が選びやすいでしょう。
選び方2:スーパーマーケットで購入する
2つ目は、スーパーマーケットで購入する方法です。
比較的、一般受けしやすい商品が揃っているため、大きな失敗を避けやすいと言えます。極端に個性的なワインが置かれていないため、初心者でも安心して選びやすいというわけです。
大切なのは、最初から完璧を求めすぎないこと。ナチュラルワインとの出会いを楽しみながら、少しずつ自分の好みを見つけていくと良いでしょう。
選び方3:専門店でアドバイスをもらう

3つ目は、ワイン専門店で相談しながら選ぶ方法です。
経験豊富なスタッフが好みや予算に合わせてアドバイスをくれるので、より自分に合ったワインに出会える可能性が高くなります。
お店では、「どんな料理に合わせたいか」「普段どんなワインを飲んでいるか」など、自分の嗜好を具体的に伝えてみましょう。そうすることで、マッチ度を上げることができます。
深く知ることでより楽しもう!「ナチュラルワイン」とは?
ここからは少しだけお勉強の時間。「そもそもナチュラルワインとは」なんてウンチクを語りながら友人や恋人、家族と楽しい時間が過ごせるよう、ナチュラルワインについて分かりやすく解説していきましょう。
ナチュラルワインの特徴
一般的なワインと比べて、ナチュラルワインにはどんな特徴があるのでしょうか。大きく分けて2つの工程に注目してみましょう。
1つ目は、ブドウ栽培へのこだわり。化学肥料を使わず、農薬も最小限に抑えた有機栽培を行っています。特に日本のように湿気が高く雨の多い気候では、完全な無農薬栽培は難しいもの。それでも、できる限り自然に寄り添った栽培方法が選ばれています。
2つ目は、醸造過程での特別な配慮。通常のワイン造りでは、天候不順で糖度が足りない場合は糖分を加えたり、温暖化の影響で酸味が足りなければ酸を補ったり、輸送時の品質維持のために酸化防止剤を使ったりすることが一般的です。これに対してナチュラルワインは、糖分や酸の添加、酸化防止剤の使用といった人工的な調整を極力避け、その土地で育ったブドウ本来の個性をありのままに表現することを大切にしています。
ナチュラルワインの誤った知識
ここで、よくある誤解について触れておきましょう。「濁っているワインがナチュラルワイン」というイメージを持つ人が多いのですが、実はこれは大きな勘違い。濁りの有無は単にフィルター処理の違いであり、ナチュラルワインの本質とは関係ありません。むしろ大切なのは、その土地ならではの特徴を活かし、できるだけ手を加えずにワインを造ろうとする姿勢です。
また一般的には、保存料が未使用のため「ナチュラルワインは早めに飲むほうが良い」と言われていますが、必ずしもそうではありません。適切に保存することができれば、しっかりと造られた良質なナチュラルワインは、熟成による味わいの変化も楽しめます。
例えば、あの高級ワインの代名詞「ロマネ・コンティ」も、実はこうしたナチュラルな製法で造られています。つまり、ナチュラルワインは決して一時的な流行ではなく、伝統的なワイン造りの理念そのものと深く結びついているのです。
日本におけるナチュラルワインの生産事情
日本のワインといえば、真っ先に思い浮かぶのは山梨県でしょう。他にも、北海道の余市エリア、長野県、山形県など、各地で個性豊かなワインが造られています。しかし、どの産地のワインが良いというわけではありません。大切なのは、その土地の特徴を理解し、丁寧にワインを造り上げる生産者の姿勢と技術力。各地の生産者たちは、日本の気候や土壌に合わせながら、できるだけ自然な方法でワインを造ろうと挑戦を続けています。
最近では、地方自治体もワイン産業を地域の未来を担う産業として注目。醸造免許の取得をサポートするなど、新規参入を後押しする動きも活発化しています。その結果、各地で意欲的な生産者が増え、日本のワイン産業は着実に広がりを見せています。
ただし、いくつかの課題もあります。最も深刻なのは、ブドウ畑の確保です。新たにワイン造りを始めようとしても、まとまった広さの畑を見つけることは容易ではありません。さらに気がかりなのは、事業の継続性です。情熱を持ってワイン造りを始めても、採算が取れず趣味的な生産に留まってしまうケースも少なくありません。
この状況を踏まえると、優れた醸造技術の習得だけでなく、次世代に引き継げる収益性の高いビジネスモデルの確立も、日本のワイン産業が直面する重要な課題と言えるでしょう。
【番外編】ナチュラルワインに合う料理

「白ワインは魚料理、赤ワインは肉料理」誰もが一度は耳にしたことがある、ワインと料理の黄金ルール。でも実は、ナチュラルワインは和食との相性が抜群です。ぶどうの品種などにもよりますが、白のナチュラルワインは、比較的、新鮮な刺身との相性がいいものが多いです。素材本来の味わいを引き立て、より豊かな食事の時間を演出してくれます。
まるで日本酒のように繊細な料理に寄り添い、かつワインならではの深い味わいを楽しめる――これが、ナチュラルワインの持つ独特の魅力なのです。ただし、これも絶対的なルールではありません。ワインの品種や造り手によって、それぞれ個性的な表情を見せてくれるでしょう。
とはいえ、初めてナチュラルワインを楽しむ際は、まずは定番の組み合わせからスタートすることをおすすめします。白ワインなら新鮮な刺身、赤ワインならジューシーなステーキなど、親しみやすい料理と合わせてみましょう。そこから少しずつ、「この料理にはこのワインが合うかも」と冒険してみるのも楽しいものです。
また、マグロのような赤身魚は白ワインより軽い赤ワインと驚くほど相性が良かったり、さっぱりとした鶏肉料理ならしっかり目の白ワインがぴったりだったり。同じステーキでも、シンプルに塩こしょうで味わうのか、濃厚なソースを添えるのかで、合わせるワインが変わってくることもあります。
大切なのは、固定概念にとらわれすぎないこと。あなたの好みやその日の気分に合わせて、自由に組み合わせを楽しんでみてください。そうすることで、きっと新しい発見があるはずです。
プロおすすめのナチュラルワイン2選
「選び方は分かったけど、具体的にどのワインを選べばいいの?」そんな声にお応えして、ナチュラルワインの専門店「小松屋」から、初心者の方にもおすすめの2本をご紹介します。どちらも手に取りやすい価格帯で、日々の食卓を特別な時間に変えてくれる魅力的なワインです。
まず1本目は、スペインの海風が育んだ白ワイン「アルバリーニョ」。2,000~3,000円という入門に最適な価格帯ながら、その実力は折り紙付きです。スペイン沿岸部で造られるこのワインは、魚介類との相性が抜群。日本と同じように魚介を愛する国スペインの食文化の中で育まれた「アルバリーニョ」は、刺身や生牡蠣はもちろん、和食全般とも見事にマッチします。
2本目は、日本が世界に誇る赤ワイン「マスカット・ベーリーA」。生産者のタケダワイナリーは、1920年の開園以来「良いワインは良い葡萄から」をモットーに、土づくりから始める葡萄栽培、無濾過・酸化防止剤不使用でのワイン醸造を続けています。日本で品種改良されたベーリーA種を使ったこのワインは、ブドウ本来の味わいをじっくり堪能できる味わいが特徴です。濃縮感や力強さが感じられます。
また、幅広いお料理とも好相性で、普段の食卓に寄り添い、そして華を添えてくれます。3,000円前後で楽しめるコストパフォーマンスの高さも魅力と言えるでしょう。
まずは、この2本のワインから、あなたのナチュラルワイン探求の旅を始めてみませんか?きっと、ワインの新しい魅力に出会えるはずです。

| 品種 | アルバリーニョ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 生産地 | スペイン |
| 保存方法 | 冷暗所に保管 |
| 商品ページ | ナチュラルワイン専門オンラインショップ |
| 品種 | マスカット・ベーリーA |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 生産地 | 日本 |
| 保存方法 | 冷暗所に保管 |
| 商品ページ | ナチュラルワイン専門オンラインショップ |
※詳細は商品ページでご確認ください。
この記事のまとめ
| ナチュラルワインの一般的な特徴 |
|
|---|---|
| 選び方のポイント |
|
| 食事との相性 |
|
| 誤った知識 |
|
| 保存・楽しみ方 |
|
| おすすめ商品 |
|

観光協会おすすめの「ドライブデート」企画や、「プロに聞くアドバイス」企画の編集を担当。地方移住に関する取材経験が150本と豊富で、各地の名所に精通。プライベートでも週2回はドライブするほどのドライブ好き。
